2013年12月7日
iPhone版ドラゴンクエスト、無事クリア
すっごく懐かしいゲームがiPhoneで復活したということで、忙しいのについつい手を出してしまいました。ドラゴンクエストⅠです。
原作が世にリリースされたのが1986年とのことですので、かれこれ30年近くも前のゲーム。実際に今回触ってみたけど、一つもストーリーを覚えておらず、しかもキャラクターが四六時中こちらを見ていた当時のゲームよりも進化していて、なんとも技術の進化を痛感させられるわけです。
ゲームの構成はとてもシンプル。
世界が危険になって、お姫様が連れさられ、勇者が登場。お姫様を救出して世界に平和が戻り、勇者とお姫様が結ばれる・・・。
鉄板ですね。
レベルも24でクリアしまして、合計時間は10時間くらい?
大人になってゲームにハマることはなくなりましたが、ちょっと頭を休める程度にスマホでゲームできるのも悪くないですね。
今後どんどんこういうゲームもスマホでできるようになるんでしょうけど、やるかやらないかと言えば、やはりもうやらないかな(笑)
2013年12月6日
成長のチャンスが舞い込んで来る仕組み
昨日は、2013年度公益社団法人茅ヶ崎青年会議所(茅ヶ崎JC)の卒業式でした。今年入会した私にとっては初めての卒業式。茅ヶ崎青年会議所は特に規律というか格式を大切にしていて、卒業式も相当丁寧にしつらえてます。今回は、卒業生のメッセージからJC運動について考えてみたいと思います。
「JCは人をつくり、仲間ができる場所」
これは、卒業生の皆さんが異口同音でお話しをされていることです。JCには多数の事業を単年度でこなしていきますが、それらは参加者に経済的なメリットを与えるわけではなく、むしろ仕事の時間も圧迫しながら活動をするため、どちらかというとしんどい日々です。
しかしながら、そのハードな日々をタイムマネジメントしながら本業をきちんと続けていく過程で、事業も一個人としてもとても大きく成長ができます。メンバーで暇な人なんていませんので、お互いに気遣い、役割分担をしながら切磋琢磨し、その結果として何ものにも代えがたい友情ができる。そういう場所なのだと思います。
メンバーになり、コミットすること
とはいえ、JCのメンバーになればそれだけで成長し、仲間が増えるというものではありません。そこからさらにコミットして、主体的に動けるようにならなければ、JCの価値を十分に得ることはできないでしょう。
私はまだ半年程度で、まだよく分からないことだらけですが、まずはコミットしていくことが大切だと思ってます。別に失敗しても構わない。JCで失敗しても、誰かを傷つけることもないですし、むしろ失敗していくなかで改善をする機会に出会える。そんなふうに今は考えてます。
コミットしたくなる空気づくりを
コミットすることの大切さを私は感じていますが、それが実現できない時期というものもあります。そういう時期が続くと、今度は「JCなんて・・・」という気持ちになってしまう、それが普通の感覚だと思います。
私としては、そういう感覚を持たなくて済むような、参加できなくても何が行われているかが見える仕組みを作っていきたい。そう考えています。私は今31歳ですが、2014年度は広報委員会の幹事という役割をいただきましたので、対外的な広報もそうですが、むしろ対内的な広報活動こそが重要だと感じています。せっかくの機会なので、JCって何なのかということを自分なりに考える期間として、またコミットする人を増やすチャレンジをする期間として、頑張ってみようかなぁと思ってます。
今年入会したばかりの私にJCのことを様々な角度からお話してくださった卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。今後のご活躍を心よりお祈りしております。
2013年12月5日
ヘッドセットとして圧倒的 ― Bose Bluetooth headset Series 2
電話で手がふさがることを極端に嫌がる私は、これまでいくつかのヘッドセットを使ってきましたが、そこへの投資はせいぜい数千円でした。決して不満を抱いていたわけではないのですが、無くしてしまうことが多く、このたび新しいものに買い換えました。
それがこの「Bose Bluetooth headset Series 2 (左耳用)
価格は15,750円と結構な値段がしますが、BOSEなら納得。どちらのお店でも安売りがされていません。
正直買うかどうか本当に迷いましたが、仕事で電話が果たす役割は非常に大きいですし、電話に難があると通話の相手にも迷惑になってしまうため、ここは投資すべきと考えました。
使い心地は全く問題ありません。付け心地も耳に引っ掛けないので何の邪魔もしないですし、全然痛くもありません。お金を出すだけの価値はあります。
私はiPoneユーザー(4と4s)ですが、Bluetoothの設定は全然困りません。どんなにデジタルツールが苦手な人でも、安心して使えます。
ラジオも音楽も聴けますので、耳につけっぱなしでほぼ一日過ごせます。当たり前ですが、これは万人にオススメです。
こんなに高いのは・・・という方には、こちらの記事をご参考にしてみてくださいね。
2013年12月4日
2種類の「しごと」を持つこと ― 「仕事」と「志事」
今日は同業の先輩が主催するセミナーに出席してきました。セミナーの名は「赤沼創経塾プレミアムセミナー」というもの。いわゆる営業戦略セミナーです。
普段はこういうイベントにあまり行かない私ですが、事業を次のステージに引き上げるにあたってどうしても苦手な部分にメスを入れる必要があり、先輩の勧めにしたがって参加してきました。
仕事には二種類あります。それは、自分がやりたい仕事と食べるための仕事。前者を「志事」、後者を「仕事」として分ける人もいますが、私も同じ感覚です。この二つの「しごと」を両輪として活動しなければ、事業の持続的な発展はありません。
たとえば、弁護士や司法書士の業界では過払い金バブルなんてものが、数年前押し寄せていました。消費者金融を利用された一般の方々が、利息を払いすぎていたため、それを返還する訴訟が全国的にものすごく増えまして、そこに乗っかった弁護士や司法書士は大きな利潤を得ました。専門知識は特に不要で、契約関係の確認と計算さえできれば後は訴えるだけ。もちろん多くの人の役にも立ちましたし、社会的な正義の実現でもあったと思います。ただ、稼げるからやる、という面は少なくなかったでしょう。
他方で、このバブルに乗らずに例えば投票の価値の平等を実現するために延々と戦う法曹の方もいます。彼らは、民主主義における投票価値がいかに重要で、平等の実現に向けて突き動かされています。そこには稼ぐという目的は後退し、社会正義の実現に主目的があります。
以上のしごとについて、前者を「仕事」、後者を「志事」とあらわしますと、事業の点からすれば両方やっていかなくことが大切なのです。「志事」を達成するために「仕事」をする。家族を守るために「仕事」をする。
私は行政書士として、地域における様々な事業の最適化や、中小企業と専門的な情報や専門家をつなぐことを自分の事業目的に掲げています。これは強い地域経済を作りたいという、行政書士としての「志事」です。ただ、これはすぐに収益が上がるものではありません。その土台として、企業やNPOなどの異業態が相互にお互いの取組みを見えるような環境整備だったり、行政に情報が集まり、必要な情報が届くような環境整備をしていく必要があるので、長期的に取り組んでいくべきものです。
これをやっていくのはやりがいがありますし、面白いとも感じています。しかし、これだけやってたらただのボランティアになります。私はボランティアをするために生きているわけではない。
きちんと事業として成長させ、関係者にも利潤をもたらせる存在にならないといけないのです。
以上の考えのもと、私の事業において「仕事」の部分を強化する必要があるのでセミナーに参加しました。トレンドや皆さんに端的に必要な事業をフォローしていく。まもなく2013年は終わろうとしていますが、少し次への決意が固まりました。
本日勉強した内容については、実践しながら皆さんにご紹介させていただきます。お楽しみに。
2013年11月19日
在宅勤務の増加で変わる社会構造
Facebookで友人が次の記事を紹介していました。
「一部の業種や業務でしか利用されていなかった在宅勤務(テレワーク)が本格導入の兆しをみせている。」記事によれば、2015年には市場規模として1兆円を超えるという。
この1兆円という数字は、在宅勤務が普及することに伴うセキュリティー対策だったり、通信や設備に関わるものと思われますが、その投資を後押しするために国が調査に乗り出したという形です。
最近はCrowdWorks(クラウドワークス)が有名ですが、業務の発注を直接個人に行うことで費用を抑えたり、逆に個人が企業に属することなく仕事を受けるような仕組みが整いつつあります。企業としてもコスト削減に必要なときに必要なスキルを調達した方が、固定費用を大幅に削減できるし、主要業務に関わらない部分で人材育成をしなくて良いというのは、貴重な時間の節約にもつながります。
と、ここまで見てみるとワークスタイルの話しに収れんしてしまいますが、このスタイルが広がれば人の住む地域が変わってくることは間違いありません。仕事の中心は東京だけど住んでいるのは沖縄、なんてことはもう既に現実化しています。
なにもこれはIT企業に限ったことではありません。「現場」というのが欠かせない仕事は別として、ほとんどの仕事はこの形態に移行することが不可能ではないのです。
それをつき進めていくと、「住みたいところに住む」ということが可能となり、生活拠点の選択肢が広がり、それこそ地域間競争が生まれていきます。教育が充実していたり、緑が多かったり、給付が多かったり・・・様々な特色を売りにして地域が独自性を発揮することが期待されるわけです。
そうして人の動きが変わっていったとき、今のあなたの仕事はどうなるでしょうか?
地方で恩恵を受ける人、都心で恩恵を受ける人、人の生き方が多様化するのは実はこれからなのかもしれませんね。どんどん準備をしていきましょう。
2013年7月28日
「捨てる」にこだわる
しばらく更新が滞ってしまいました。先月の後半くらいから立て続けに急ぎの仕事が入り込み、新しい組織やグループに入ったことで時間を急激に圧迫。ひとまず参加することや始めることに意義を見つけてきたけど、いろいろ手を出した結果何もできないという最悪の結果を出さぬよう、しばらく「捨てる」ということを最重要課題に持ち上げています。
モノをこれまで以上に捨てて、データ化できるものはすべてデータ化する。会議や打ち合わせの時間短縮にもこだわり、使うもの・使わないものなどをドライに切り分けていく。そうやって、自分に本当に必要なものまでスリム化しながら、状況に適合していくのが一番早い成長ルートだと考えています。
そして、これには一つ重要なポイントが。それは「空気を読まないこと」です。
文化論などでは日本人は「世間」というものが異常に自分を制約するといいます。これは体感でわかる。
でも、周囲の目ばかり気にしてたら時間がいくらあっても足りません。誰のために生きるか。それは自分の愛する人たちのためだったり、自分のためです。
その中心を大切にしつつ、同時により広く社会のために貢献できることを実施していく。それが継続性を生み、自分と社会との発展を生み出します。そのバランスが崩れてしまうなら、優先順位が自分の中で低いものをひとまず切る(捨てる)ことも、長期的に見て必要になります。
捨てることへのネガティブな効果はいつも心配されますが、大丈夫。自分が抱えていることのほとんどは、捨ててしまってもとるに足らないものですから。優先順位、大切にしましょう。
モノをこれまで以上に捨てて、データ化できるものはすべてデータ化する。会議や打ち合わせの時間短縮にもこだわり、使うもの・使わないものなどをドライに切り分けていく。そうやって、自分に本当に必要なものまでスリム化しながら、状況に適合していくのが一番早い成長ルートだと考えています。
そして、これには一つ重要なポイントが。それは「空気を読まないこと」です。
文化論などでは日本人は「世間」というものが異常に自分を制約するといいます。これは体感でわかる。
でも、周囲の目ばかり気にしてたら時間がいくらあっても足りません。誰のために生きるか。それは自分の愛する人たちのためだったり、自分のためです。
その中心を大切にしつつ、同時により広く社会のために貢献できることを実施していく。それが継続性を生み、自分と社会との発展を生み出します。そのバランスが崩れてしまうなら、優先順位が自分の中で低いものをひとまず切る(捨てる)ことも、長期的に見て必要になります。
捨てることへのネガティブな効果はいつも心配されますが、大丈夫。自分が抱えていることのほとんどは、捨ててしまってもとるに足らないものですから。優先順位、大切にしましょう。
2013年6月22日
人の動きを生み出すために|茅ヶ崎CollaVolがオープン!
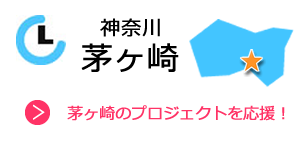.png)
今回は、CollaVolの利用方法を改めて知っていただき、茅ヶ崎CollaVolで現在募集されている情報を見ていきたいと思います。CollaVolを通じて新しい価値を生み出してみてはいかがでしょうか?(― Blogging Worker’s Style)
2013年6月4日
31歳の抱負、3つのスリム化
.png)
実は先日、私の誕生日を迎えました。盛大なパーティーをとり行い、とでも言いたいところですが、朝から仕事で夕方にジョギングシューズとジョギングバッグを買い(誕生日プレゼント)、夜は家族で食事をする、というごく普通の(でもちょっと贅沢な)一日を過ごしました。
せっかくの節目なので、1年の目標というか抱負を考えたのですが、わりとすぐに決定。それが「スリム化」です。
2013年5月30日
新しいチャレンジをするならサクッと概観して、まずは一歩踏み出す

だったら、まずはサクッとその分野について本を読んだり人に話を聞いて、後は一歩踏み出してみることをお勧めします。
2013年5月29日
年に一度の定時総会は透明性と信頼性を担保する場
.png)
昨日は行政書士になって以来初めて神奈川県行政書士会の定時総会に参加してきました。
総会は、日々の団体としての活動に会員からの支持を受けているという正統性を基礎づける場所ですが、執行部に関わっていない者が執行部の活動内容を理解する場所でもあります。
2013年5月27日
Squareでスマホクレカ決済は確実に普及する!?
.png)
2013年5月26日
【レポート】企業×NPO×行政の交流サロンⅠを開催しました
2013年5月24日(金)、茅ヶ崎商工会議所で『企業×NPO×行政の交流サロンⅠ』を開催しました。私の所属するNPOサポートちがさきと茅ヶ崎市との共同事業の一環です。市内企業、市内NPO、行政職員が膝を交えて協働について考え、交流を深めるイベントです。
今回はそのイベントについて簡単なレポートを。( ー Blogging Worker's Style )
2013年5月23日
求められてるのは、高いスキルと空気を読まないチカラ?
自由に仕事をするためには、空気を読まないことが大切。最近そんな風に感じます。
ハフィントンポスト日本版で谷本真由美さん(@May_Roma)のインタビューが掲載されています。
 メイロマさんインタビュー「『いまの日本』が当たり前じゃないと気づいてほしい」―「いま、日本で働く」ということ(3)
メイロマさんインタビュー「『いまの日本』が当たり前じゃないと気づいてほしい」―「いま、日本で働く」ということ(3)
この記事は、海外での働き方の実状に詳しい谷本さんの視点で「日本で働くこと」について書かれています。
ハフィントンポスト日本版で谷本真由美さん(@May_Roma)のインタビューが掲載されています。
この記事は、海外での働き方の実状に詳しい谷本さんの視点で「日本で働くこと」について書かれています。
2013年5月22日
「社会貢献による付加価値」(2) NPOとの正しい連携がキー
NPOとの連携は「社会貢献による付加価値」を実現しやすいやり方です。
これまでこのブログでもCSRやCSVについて取り上げてきましたが、企業活動にとって社会貢献というのは現在は「本業促進のため」に行われることが受け入れられる土壌が整ってきました。以前は「結局カネのためでしょ?」というように批判的に捉えられがちでしたが、最近は「本業の促進につながることがイノベーティヴなことだ」と肯定的に捉えられてます。
ただ、これはやり方を間違えると「嫌らしい企業」と捉えかねられないものであることに違いはありませんので、丁寧に取り組むことが必要です。
これまでこのブログでもCSRやCSVについて取り上げてきましたが、企業活動にとって社会貢献というのは現在は「本業促進のため」に行われることが受け入れられる土壌が整ってきました。以前は「結局カネのためでしょ?」というように批判的に捉えられがちでしたが、最近は「本業の促進につながることがイノベーティヴなことだ」と肯定的に捉えられてます。
ただ、これはやり方を間違えると「嫌らしい企業」と捉えかねられないものであることに違いはありませんので、丁寧に取り組むことが必要です。
2013年5月21日
「社会貢献による付加価値」(1) 価格戦争に巻き込まれないために
.png)
しかし、競争力のある市場でスピードや安全性で勝負するには、なかなか厳しい現実もあります。そこで、もっともリスクが少なく、コスト負担も場合によってはほとんど必要としないのが「社会貢献」です。
2013年5月20日
第3の習慣化に向けて|iTunesUで意欲さえあれば誰でも上質な学びの機会
学ぶ意欲さえあればいくらでも学べる時代に突入しています。
先日、アップルが提供するiTunesUというサービスで、ダウンロード数が10億を超えたと発表されました。10億というともうワケの分からない数字ですが、とにかく10億の学びが生まれているわけです。
今さらですが、これは本当にすごい。
今さらですが、これは本当にすごい。
2013年5月19日
弁護士と行政書士の違いは語っても仕方がないくらい別の職種
弁護士が行政書士を叩いているという話をTwitterで知り、読んでみると「まぁ仕方ないでしょう」と思うので、私の今の考えを書きたいと思います。話しの流れは下記のまとめ記事が分かりやすいです。
 弁護士小川義龍氏の行政書士批判 - Togetter
弁護士小川義龍氏の行政書士批判 - Togetter
2013年5月18日
シニア起業はNPOを入口に考えるといい
シニア世代の第2の人生(セカンドライフ)に関する選択肢が広がっていますね。ゆっくり過ごす方もいれば、ボランティアや農業に趣味として従事する方もいます。NPOに入って社会貢献事業に動き回る人もいます。
このようなシニア世代の活動は、まだまだごく一部の男性に限られており、実際のところ「自分がどうすれば良いのか分からない」と感じて、ただ何となく時間が過ぎていくのを感じる人が多いと聞きます。
この「どうすれば良いのか分からない」という感覚は何となく想像できますよね。現役時には仕事で都心に通う日々だったために、住んでいる地域で横のつながりを持つことができず、定年後に次へのステップが見出しづらい。その結果、持っている知識と知恵とノウハウが社会に広がらなくなってしまいます。それはとてもモッタイナイことです。
このようなシニア世代の活動は、まだまだごく一部の男性に限られており、実際のところ「自分がどうすれば良いのか分からない」と感じて、ただ何となく時間が過ぎていくのを感じる人が多いと聞きます。
この「どうすれば良いのか分からない」という感覚は何となく想像できますよね。現役時には仕事で都心に通う日々だったために、住んでいる地域で横のつながりを持つことができず、定年後に次へのステップが見出しづらい。その結果、持っている知識と知恵とノウハウが社会に広がらなくなってしまいます。それはとてもモッタイナイことです。
街の個性は街との関わり方をとことん考え抜かないと気づかないと思う
「茅ヶ崎は住みやすい」「茅ヶ崎が好き」という言葉は多くて嬉しいですし、私も感じています。しかし、具体的に「住みやすい」とはどういうこと?隣の平塚市でも藤沢市と比べて何が違うの?という疑問に、ずっと答えられないできました。
私たちの多くは、「住みやすい」という評価をするとき、自分基準でおこないます。しかも、明確な根拠はなくて、「住み慣れた」「良い思い出が多い」「雰囲気が良い」という素朴な感覚に基づいて判断していたりするんじゃないでしょうか。少なくとも私はそうでした。
しかし、この街でどこまでやれるか、自分が考える必要だと思うことを徹底してやれるか、ということを突き詰めて考えて動いてみると、「もしかしたらココの風土は自分に合わないのかもしれない」という感覚になることがあります。考え抜いていくと、自分がやろうとしていることが先鋭化していきますので、小さな異物感に反応しやすくなるのです。
私たちの多くは、「住みやすい」という評価をするとき、自分基準でおこないます。しかも、明確な根拠はなくて、「住み慣れた」「良い思い出が多い」「雰囲気が良い」という素朴な感覚に基づいて判断していたりするんじゃないでしょうか。少なくとも私はそうでした。
しかし、この街でどこまでやれるか、自分が考える必要だと思うことを徹底してやれるか、ということを突き詰めて考えて動いてみると、「もしかしたらココの風土は自分に合わないのかもしれない」という感覚になることがあります。考え抜いていくと、自分がやろうとしていることが先鋭化していきますので、小さな異物感に反応しやすくなるのです。
2013年5月16日
「地域で商売するなら地域に還元すること」はなかなかできることではないけどやってる人がいる
日本を支えるほとんどの企業は、「あの会社が何をしているか」ということが地域住民から知られていないことが普通です。でも、よくよくあなたの地域を想像してみてください。活躍している企業を思い返してみると、その会社が何をしているか知られていることが多くありませんでしょうか。
一人の大工さんが、「今後は下請けではなくて自分で直接お客さんから依頼を受けなくちゃならない」「そのためには地域住民に知ってもらうことが大切だ」と考えて、若いうちから地域との関わりを大切にしたリフォーム会社があります。スズキ企画さんです。
一人の大工さんが、「今後は下請けではなくて自分で直接お客さんから依頼を受けなくちゃならない」「そのためには地域住民に知ってもらうことが大切だ」と考えて、若いうちから地域との関わりを大切にしたリフォーム会社があります。スズキ企画さんです。
2013年5月15日
既存のサービスを組み合わせればほとんどのサービスはカタチ作れる
小規模な企業でも、既存のサービスを組み合わせれば製品開発コストをかけずとも新サービスの提供は可能になります。そういう時代になりました。
昨日、「ChatWork(チャットワーク)」の導入について触れましたが、早速無料バージョンから有料バージョンにアップさせました。有料バージョンと言ってもパーソナルプランという月額380円の非常にリーズナブルなプランです。しかし、その効用は一瞬にしてペイできると思います。
昨日、「ChatWork(チャットワーク)」の導入について触れましたが、早速無料バージョンから有料バージョンにアップさせました。有料バージョンと言ってもパーソナルプランという月額380円の非常にリーズナブルなプランです。しかし、その効用は一瞬にしてペイできると思います。
2013年5月14日
CSRを経営に活かすという視点はとても難しいけどチャレンジし甲斐がある
以前CSV(企業価値創造:Creative Shared Value)という概念についてこのブログでご紹介させていただいたことがありました。CSR(企業の社会的責任:Corporate Social Responsibility)という「責任」的な側面の強調ではなく、それ自体を経営に直結させてビジネスとして社会的な課題にアプローチすることを指します。
そうは言っても、この本質を理解するのはとても難しい、というのが私の感想です。自分たちのビジネスをいったん抽象化して、社会的な課題とマッチングさせるカタチで具体的なモデルに落とし込む。書いてて「ふわふわし過ぎだな」と感じざるを得えません。
そこで、次の「責任ある競争力」という本を書店で見つけました。
2013年5月13日
反復継続しなければならないので何を習慣にするかはしっかりと「選ぶ」必要がある
ちょうど昨年の今ごろ、私はフルマラソン出場を宣言しました。
 Blogging Worker's Style: フルマラソン・チャレンジ日誌はじめます|「走る」って言っちゃったし
Blogging Worker's Style: フルマラソン・チャレンジ日誌はじめます|「走る」って言っちゃったし
というか、今見たら昨年の5月13日(今日)に宣言。あれからもう一年経ったのかという感覚と、まだ一年かという感覚の両方があります。ここまで「走る」ことが日常に溶け込むことになるとは、当時の私には思いもよらないところです。
人は習慣の生き物だと思います。何かを身に付けたければまず習慣化するのが一番、なりたい自分に近づくためにはなりたい自分が実践しているであろう習慣を身に付けるのが一番、というように私は考えています。
というか、今見たら昨年の5月13日(今日)に宣言。あれからもう一年経ったのかという感覚と、まだ一年かという感覚の両方があります。ここまで「走る」ことが日常に溶け込むことになるとは、当時の私には思いもよらないところです。
人は習慣の生き物だと思います。何かを身に付けたければまず習慣化するのが一番、なりたい自分に近づくためにはなりたい自分が実践しているであろう習慣を身に付けるのが一番、というように私は考えています。
2013年5月10日
LINE・Skype・050plusなどのアプリを仕事で使うことはアリか?
LINEやSkypeといった無料通話アプリや、NTTが出している050plusなどのサービスを仕事で使うことについて、そもそも商用利用することが可能なのかどうか以前から漠然と気になっていました。
そこで、
という2段階で考えてみました。
そこで、
- 規約的にありかどうか
- 質的にありかどうか
という2段階で考えてみました。
2013年5月9日
イベントの集客とサービス業の集客|「話題性」を作るのはとても難しい
コンテンツとその拡散(集客)には「話題性」が欠かせない。そんなことを考えてました。
先日、スポーツオブハートというイベントに参加する機会があり、日中の仕事を終えて大急ぎで代々木体育館に行ってきました。
この3点を目的としたチャリティーイベントです。参加者はチケットを購入し、障害者スポーツを楽しんだり、夜に行われるアーティストのライブに参加することができます。
 スポーツオブハート ~スポーツ×文化の祭典~
スポーツオブハート ~スポーツ×文化の祭典~
先日、スポーツオブハートというイベントに参加する機会があり、日中の仕事を終えて大急ぎで代々木体育館に行ってきました。
◆スポーツオブハートとは?
- 障害者スポーツの支援を行うこと
- 障害のある子もない子も、同じというノーマライゼーションの考え方を育てること
- 東京オリンピック・パラリンピック招致をアピールすること
この3点を目的としたチャリティーイベントです。参加者はチケットを購入し、障害者スポーツを楽しんだり、夜に行われるアーティストのライブに参加することができます。
2013年5月8日
ボランティア活動を「無償の提供」ではなく「吸収の機会」と捉える
皆さんはボランティアと聞くとどのようなイメージを持つでしょうか?ゴミ拾いなどのクリーン活動はイメージしやすいものかもしれません。
 ほのぼのビーチ 茅ヶ崎 - 美しく誰にもやさしい理想的な海浜をめざす
ほのぼのビーチ 茅ヶ崎 - 美しく誰にもやさしい理想的な海浜をめざす
さて、では「ボランティア」という言葉の具体的な中身は何でしょうか?ゴミ拾いという、本来自分に義務のないことを社会のために無償でおこなう、というような感じでしょうか。
実際、ボランティアという言葉は「自発的」で「無償」で「利他的」な活動と表現されます(ウィキペディアでは「先駆性」も挙げられています)。
この中でも、特に「無償」というイメージが強いと思いますが、そもそも「無償」であることと「無価値」であるということとは全く別のものです。
さて、では「ボランティア」という言葉の具体的な中身は何でしょうか?ゴミ拾いという、本来自分に義務のないことを社会のために無償でおこなう、というような感じでしょうか。
実際、ボランティアという言葉は「自発的」で「無償」で「利他的」な活動と表現されます(ウィキペディアでは「先駆性」も挙げられています)。
この中でも、特に「無償」というイメージが強いと思いますが、そもそも「無償」であることと「無価値」であるということとは全く別のものです。
2013年5月7日
ゴールデンウィークも終わったことだし、4時ラー復活とブログのほぼ日更新はじめます
とうとう我らのゴールデンウィークが終わってしまいました。これから梅雨に突入して一気に夏を迎えるわけですが、暖かくなってきたことですし、4時ラーを久々に始めることにしました。
※4時ラー:4時台に起きて活動すること。厳密には4時に起きることを指すはずですが、それはキツいので4時「台」でいきます。
※4時ラー:4時台に起きて活動すること。厳密には4時に起きることを指すはずですが、それはキツいので4時「台」でいきます。
2013年4月30日
チャレンジを重ねていくと、精神的なハードルが下がるらしい
.png)
先日、現在進行中のプロジェクトなどを簡単に紹介させていただきましたが、ふと振り返ってみると、自分の中でチャレンジへのハードルが随分下がっているなぁと感じています。今日はそんな感想と意気込みを書いて、ブログ更新のきっかけに。(― Blogging Worker’s Style)
2013年4月21日
圧倒的に簡単にレスポンシブなサイト作成が可能|Striking.lyを使ってみた
「特別なスキルがなくてもホームページが作れます」なんてフレーズ、もうそこらじゅうで見るようになりました。「直感的につくれる」「あっという間」と、最近のお手軽サービスの波の中、本当に簡単ですごくお洒落なサイトを作れてしまうサービスを発見。Striking.lyというサービス。早速使ってみました。
2013年4月16日
掛川・新茶マラソン、何とかゴール|仕事もマラソンも日々準備
.png)
2013年4月14日、静岡県掛川市で開催された「掛川・新茶マラソン」(フルマラソン)に出場してきました。日本で最も過酷なコースと評される本レース。想像していた通り、ハンパじゃないほどにキツイ42.195kmでした。
今回はそんな過酷なレースのご紹介と、久々に一人でホテルに泊まりながら考えた「日々の準備」の大切さについて書いてみたいと思います。(― Blogging Worker's Style)
2013年4月11日
マッチングプロジェクト再考に『ノーリスクで儲かる仕組みをつくる「コラボ」の教科書』
.png)
私はNPOにも所属して、企業とNPOとをかけ合わせていくプロジェクトを進めています。しかし、言うは易しというもので、なかなかその効用というか意義みたいなものが伝わらない。やっている私たちも具体的に「じゃあどうすれば」というところでこれまでも模索してきました。
が、そろそろ私の中では答えは出てきています。ということで、今回は一冊の本をご紹介します。その名も『ノーリスクで儲かる仕組みをつくる「コラボ」の教科書』。(― Blogging Worker's Style)
2013年4月10日
近況報告|「つなげる」というポジショニング
最近まったくブログ更新できていませんが、忙しかったり、考え事してたり、失敗してしまったりと、書くに書けない状況で猛スピードで時間が過ぎている感じです。
今日は一息つける時間があるので、そのあたりを整理するエントリーを一本。(― Blogging Worker's Style)
今日は一息つける時間があるので、そのあたりを整理するエントリーを一本。(― Blogging Worker's Style)
2013年3月20日
【KEIEIコンビニ出店レポ②】TOPページの作成からイライラする、の巻
.png)
先日、株式会社ワンズマインドさんが提供するKEIEIコンビニで実験的に出店するということをこのブログで書きました。
今回はマイページのTOP画面作成について、レポートいたします。(― Blogging Worker’s Style)
2013年3月19日
ROBINS|まだまだ道のりは遠いです・・・
.png)
これまでにこのブログでも、ホームページ上でもお知らせしてきましたが、現在ROBINSというサービスのパイロット運用中で、掲載協力企業を募集している段階です。
今回はそんなROBINS普及活動中の現状について、私が考える課題と可能性について、ざっくばらんに考えたいと思います。「ROBINSって?」と思われる方だらけだと思いますので、「へぇー」って程度にご覧いただけると良いかなぁって思います。(― Blogging Worker’s Style)
2013年3月18日
ソーシャルメディア活用論者はまだまだマイノリティー|安藤美冬さんが「いいとも!」登場
僕が接する情報からすると、「twitterを活用して・・・」「ノマドワーカー云々」という話題は結構多い印象を受ける。でも実際は超マイノリティー。
本日、安藤美冬さんが笑っていいともに出演しました。なぜ!?と思ったけど、きっと会場は凍り付くだろうと思いながらハラハラしながら視聴した感想を。( ー Blogging Worker's Style )
2013年3月15日
Google リーダーの終焉|乗り換えサービスの検討と、無料サービスの弱さを考える
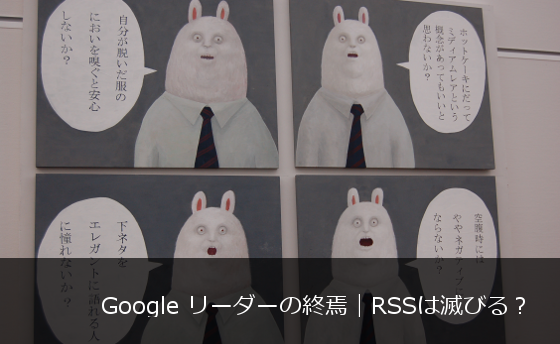.png)
Googleリーダーが突然7月にサービスを終了すると発表しました。ユーザー数の減少が原因とのことですが、その割りにTwitterやブログでざわつきが見られます(そういう人をフォローしている私の原因だとおもいますが。)。
かくいう私もGoogleリーダーのヘビーユーザーですので、代替サービスへの乗換えを検討しています。早速Web上で代替サービスの紹介が広く行われているようですので、いくつかピックアップしつつ、今回のサービス終了について考えてみたいと思います。(― Blogging Worker’s Style)
【KEIEIコンビニ出店レポ】レポートはじめます
皆さんの中にも日々営業の攻勢に遭い、本当は必要でもないものを購入してがっかりな思いを頂いている方は少なくないでしょう。
今回、士業の中の多くも営業メールが来ていると話題に出た「KEIEIコンビニ」というサービスを利用してみることにしましたので、ご報告と合わせて、一体全体どのようなサービスなのかを随時レポートしたいと思います。良いサービスであれば皆さんも利用する価値がありますし、「むむっ」というサービスであれば「むむっ」ということで。(― Blogging Worker’s Style)
本当に実現可能?|知識サポート・経営改革プラットフォーム(中小企業庁)
.png)
「100万社以上の中小企業・小規模事業者と1万以上の専門家・先輩経営者等とをつなぎ、実践的な知識・ノウハウの共有やビジネスマッチング等を実現する」
「バーチャルコーポレーション:ITプラットフォームを通じて、例えば、設計、製造、実証をおこなうそれぞれの企業が連携するなど、複数の業種の中小・小規模事業者のビジネス連携を実現する」
・・・違和感を感じずにはいられないのですが(― Blogging Worker’s Style)
2013年2月28日
価値の創出に向けた仲間作り!ソーシャルメディアの本当の使い方を考える(行政書士のケース)
.png)
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、社会保険労務士、そして行政書士と言った、いわゆる「●●士」というサムライ業は、超フリーランス的な仕事だというのが僕の考え。これらの仕事は、「その人自身」が商品なのであって、ソーシャルメディアで情報発信していくことが向いている職業だと思うのです。
ところが、これらの職業で実際にソーシャルメディアを駆使して、個人を売っている人はほとんどいません。そこで今回は、僕が考える「行政書士とソーシャルメディア」の関係について書いてみたいと思います。ホームページ、ブログ、Twitter、Facebookといろいろある媒体でどれをどのように活用すべきか、同業者の方に考えて頂くきっかけになれば幸いです。(― Blogging Worker’s Style)
2013年2月20日
いよいよスタート!ROBINSによる「信頼」と「取引の促進」の紹介

インターネット上に存在するホームページや各種サイトが本物かどうか、運営している主体が存在する会社なのかどうか、そういう「信頼」を一目(ひとめ)で裏付けるサービスが始まりました。サービスの名前は「ROBINS(ロビンズ)」です。
早速ITPro(日経コンピュータ)で記事として採り上げられましたので、皆さんにも紹介したいと思います。なお、質問・疑問・ご意見等はMessageLeafよりお願いします!(― Blogging Worker’s Style)
2013年2月16日
ココナラで2件頂いたお仕事から感じること|僕のニーズとのマッチ

ココナラで出品して3週間くらいが経ちました。3週間前には4000件くらいの出品数が本日現在5200件を超え、スマホに対応し始めたりと、ユーザー数の増加とシステムの改善が目に見えて分かるスピードです。
私もこの3週間で2件の有料相談と1件の無料相談の計3件を受注。
今回は有料相談2件受注による感想と、展開について簡単に考えてみたいと思います。(― Blogging Worker’s Style)
2013年2月8日
【レポート】CSVというパラダイムシフト|企業とNPOのパートナーシップ東京交流会に参加してきた
.png)
2013年2月6日、赤坂ツインタワーで開催された一般社団法人SAVE TAKATA主催による「企業とNPOのパートナーシップ東京交流会」に参加してきました。
今回は、その基調講演のテーマである「CSRからCSVへ」を聞いて考えた企業とNPOとの協働を創出するためのアプローチについて考えてみたいと思います( ー Blogging Worker's Style )
2013年2月4日
神奈川マラソン走破!キツかったけど何とか目標達成!
.png)
今日、横浜市は磯子区でおこなわれた神奈川マラソン(ハーフマラソン)に出場してきました。天候に恵まれ、私も何とか自分の目標をクリアすることができ、良い大会でした。今回は、この大会について簡単に振り返り、今後参加される方の参考にしてもらえれば幸いです。(― Blogging Worker's Style)
2013年1月30日
コメントとメールの真ん中くらい?|MessageLeafを設置しました
.png)
そんな折、たまたま読んだ記事(最後にご紹介します!)で、MessageLeafというサービスが紹介されておりましたので、今回は当ブログにそのMessageLeafをf設置したことのご報告も兼ねて一本レビューを書いてみたいと思います(― Blogging Worker's Style)
2013年1月29日
coconala(ココナラ)はサービスの本質を突く!?|一件受注によって感じる可能性
Twitter(ツイッター)でチラッと書いたんですが、この度興味本位でcoconala(ココナラ)さんでワンコインサービス(500円)を出店いたしました。早速1件の注文をいただいたので、ココナラで商品を出展することについて思ったことをいくつか書いてみたいと思います。えー、500円ですかwとか言わずに、少し視点を変えてみると結構面白いんじゃないかな?迷っている人にはお勧めします(― Blogging Worker's Style)
2013年1月13日
【週刊読書】「視座」を明確に|『キュレーションの時代』(佐々木俊尚)
週刊読書はじめます――と書いて、3週間弱。いまだに一本しか書いていませんが、気にしません。・・・気にしてました。。
さて、本日は『キュレーションの時代』(佐々木俊尚)について。本書で『視座』という著者の視座を頂いたので、情報の洪水の中で自分はどのように行動するのかを考え直しつつ、最後に「なぜブログを書くのか」について少し触れてみたい思います。(― Blogging Worker’s Style)
2013年1月11日
コラム更新|法務は利益につながるか
.png)
ホームページで『利益を創出する法務』というコラムを書きました。私たち行政書士は基本的に小~中規模企業の法務支援や許認可の取得代行・コンサルティングを行いますが、クライアントニーズと行政書士サービスがミスマッチを起こして良い結果を生まない場合もあると聞いています。
それは単純にクライアントニーズに沿ったサービスがなされていないとバッサリ言うのは簡単なのですが、それでは何も生みません。そこで、利用する側、サービスを提供する側がどのようなスタンスなのかが予め十分に検討されていれば、双方Win-Winの関係が作れると思い書いてみた次第です(あくまでも私の考えですが)。
もし宜しければ読んでみてください。
【コラム】『利益を創出する法務』
2013年1月6日
本年もよろしくお願いします。|知恵の過剰とブログ

ご挨拶が遅れてしまいましたが、新年明けましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願いします。
年末年始はわりとバタバタしていたので年末年始“感”がほとんどなかったのですが、それでも昨年一年を通して得たモヤモヤ感を解消する一定の目途が立ってきたので、そのご紹介を兼ねて新年のご挨拶に代えさせて頂きます。(― Blogging Worker’s Style)






.png)
.png)
.png)

.png)